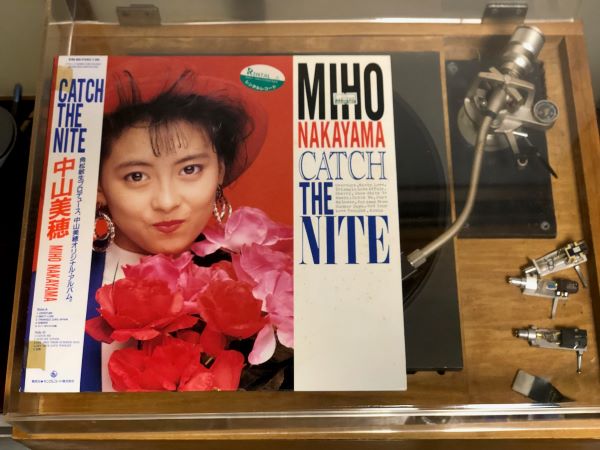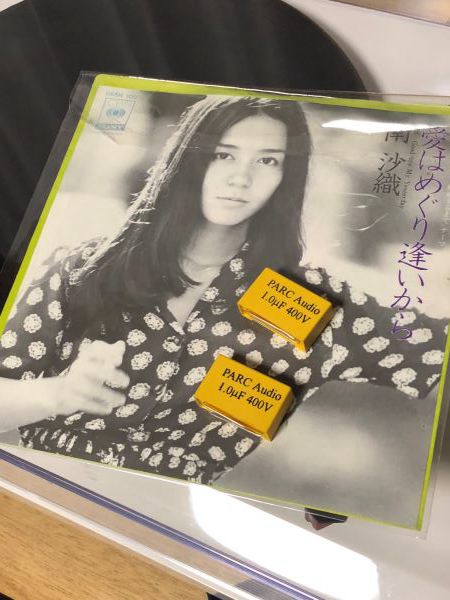1��1��

�ނ�ŐV�N�̂��c�т�\���グ�܂��B
�{�N����낵�����肢�������܂��B
�ʐ^�͍���̕��Ɛ�����킸�c�̂͂��B
�B�e�������Ⴄ���畔���̖��邳�͈Ⴄ���ȁH
���̎U�����āA���q�v�w�{��2�l�Ō��U�̂��j��������Ƃ������Ƃ�
����ł��܂���ŁA���炤������ȊO�o���邱�Ƃ������B
���������W�R��FM�Ȃ|�����肵�āc
46�N�O�ɂȂ�܂������߂Ẵo�C�N�����t��CB50JX����ɓ��ꂽ�����
�Ӗ����������̕ӂ����傢������Ă����L���B
�����̂ɂ悭����A�ƍ��Ȃ�v���܂����A
���ꂭ�炢������邱�Ƃ������H
�������������FM�����Ă��������ł��ˁB
�����l����ƍ����̂���邱�Ƃ͂����ς�������Ȃ������B
���̍��������������ǂ�����������悤�ɂȂ�܂�����
������ǂ������H���Ďv���Ă��܂��B
���Ȃ݂�AST-A10+AST-S1�Œ����Ă��܂����A
�X�P�[�����Ȃ�38�Z���`3�vay�Ƒ��F�Ȃ��B
'88�ቹ�v���͉R�ł͂Ȃ������B
1��2��
�Ƃ���ł��܂ł�38�Z���`38�Z���`�Ƃ��ꂾ�������Ă���Ɠǂ�ł�������O����͖̂����B
�����ŊȒP��2024�N�Ƃ����N���U������Ă݂����B
�i�N���̂����ɂ���Ă����H(;^��^)�j
�������ّ�ɗ��Ă��ꂽ�I�[�f�B�I�p�[�c�̃C���v���b�V�������������Ă̂��b���B
�i�����肵�����͏��O�j
���Ԃ��̑��K���ł��邱�Ƃ��������������������B
�܂��J�[�g���b�W�B���R�����H���ꂪ��Ԑ��������B
DENON DL-32��koyama�����ňȑO�����ċC�ɂȂ��Ă�����koyama����
���s�̖���ABBG�I�[�f�B�I�Ŕ������đ����ė��Ă��ꂽ�B
DL-301���v���[���[�t���ɂ��邽�߂��R�X�g�_�E���������Ǝv����
���݂�m��l�����Ȃ������������ɂȂ�B
�����A���������Ȃ��Ƃ������A�悭����ȕ����c���Ă����ȁA�Ƃ����̂�
�U�炴��S���B���ꂾ���Ŋ������Ă��܂��B
�����^DL-103�B
�������koyama�����Ŕq�����Ă��炸���ƋC�ɂȂ��Ă�����{�B
�j����i����ɓ���ċƎ҂���������������Ă�������B
�����珃�R���鏉���^103�Ƃ͌����Ȃ��̂����v�͌��ʂł���B
���������Ƃ������ɉ��Ƃ�����������Y�Ɗ������B
����ʏ���103����ɓ��ꂽ�i�̎����Ă������f�������j�̂���
����������Ԓ��̒�ԃJ�[�g���b�W�ł�����x�̐��E���`���邱�Ƃ��厖���ȁA�Ɖ��߂Ďv�����B
���邢�͂悤�₭�v�����̂�������Ȃ��B
�A���g���[��EC-15WX�B
����͏���ɕ`���Ă�����ۂƂ��܂�������ċ������B
���ɖ��Ăł킩���₷���ǂ��ɖ����Ă���B
�A���g���[�͂�����}�j�A��������X�^�[�g���āA�i�X�ƈ�ʑ�O�ɂ���H���ɃV�t�g���Ă������H
�e�N�j�J��AT-ML170�ɂ͎Q�����B
�V�F�����������悤�Ƃ������f���c
�Ȃ�ƒ[�q�̂Ƃ��낪�������O��Ă����B
�O�̂��߂������낵���C���g���ă��[�h�����O���Ă����̂ŁA����͂����h���悤�����������Ǝv���B
�ڒ��܂����S�������Ă����̂��낤�B
���P�����Â��J�[�g���b�W�̓V�F������O�����ȂǂƎv��Ȃ����ƁB
�������߂悤�Ƃ��̎��͎v�����̂������180�̐j�܂���ĊO�������Ƃ����B
�j��ML140�̕����������\���Ȃ��́B
���̎��̋��P������A���̌�VMS-20MK2�̃{�f�B������G�|�L�V�ł߂��Ă݂��B
VMS�V���[�Y���ڒ��܂������Ȃ��Ȃ�J�[�g���b�W����\�i�݂����ȕ��ŁA�قڊm���ɑʖڂɂȂ�B
������VMS�̏ꍇ�A�����[�q���̏����G�|�L�V���Ōł߂鎖�͈Ӗ�������Ƃ������K�R�Ǝv�������B
���̃G�|�L�V�ł߃J�[�g���b�W�������Ȃ��Ƃ����������Ȃ�Ƃ������͖��������B
�������S�ʓI�Ɍł߂Ă��܂��Ɩ��ĂȌ��ʂ��o��Ǝv���B
�����A���R�S�̂̏d�ʂ������Ă���̂ŁA���̕ӂ͉������l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�r�N�^�[4MD-1X���f�b�h�X�g�b�N�i�ɏo����̂͐������Ƃ������B
�����I�̖����j���ėǂ��̂��S�O�����قǂ����J���B
���̓A�b�v���C�g�Ȋ����͂��邪���������I�ŗ��h�Ȃ��́B
�����ԋC�ɂȂ��Ă����J�[�g���b�W�Ȃ����ɏ��荇���Ă悩�����B
FR�̃J�[�g���b�W�����������������̂������s����MM��FR-5E�Ƒ����B
���̃J�[�g���b�W�������ԋC�ɂȂ��Ă������̈��������MM�炵���Ȃ��Ƃ�����
FR������MM�������Ȃ�̂��A�Ƃ�����{�B
������MM��MC�ɉ�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���̕������ȗ����ʒu���B
�e�N�j�N�XEPC-250MK3�����������s���ɕߊl�B
�j�܂ꂾ��������207�̐j��}���ĉ��o�����Ă���B
�܂�Ă��Ȃ��Ă�TTDD�̂����Ń_���ɂȂ��Ă������낤�B
�݊��j�����݂���悤�����������Ď肪�o�Ȃ��B
1��3��
�v���[���[�́A�܂�SL-1300�B
�����̃t���I�[�g�v���[���[�ł���A�����y���ނƂ�������C�����y���v���[���[�B
���̎��w�̂́A���̎�̃I�[�g�v���[���[�Ō�쓮���������ꍇ�A�Â��O���X��
�O��I���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƁB
���₢��A���x���u�^���J������߂��肵�����Ƃ��B
�o�̓P�[�u�������E���ɂȂ��Ă����B���������P�[�X�͑����B
SONY PS-FL77�̓��j�A�̃R���p�N�g�v���[���[�����s�v�c�ƃe�N�j�N�X�̃��j�A�Ƃ�
�Ⴄ���E�ς������Ă��ꂽ�B
���̂Ȃ̂��H������������o�C�I�g���[�X�̐��ʂȂ̂��H
�����₷�����������ă��b�N�̒��ɏ풓�ƂȂ����B
pioneer��PA-100�̓v���[���[�ł͂Ȃ��ăg�[���A�[�����������֓���Ă����B
�W�����N�ƌ������ʼn����W�����N�H�Ǝv�����烁�C���̃E�G�C�g�����������B
��d�\�����O���̃E�G�C�g�������Ă���̂ŃW�����N�Ƃ������Ƃ��B
�������ꉞ�͎g���Ă���B
�����J�[�{���A�[���ƌ������ƂŖ��͂����邪���킩�ǂ����͂킩��Ȃ��B
KP-800�̓g���I����̌���̃��f���B���̌�880�ӂ肪�o�Đl�C�͎����čs���ꂽ��������
�������肵�����̉��̍D���v���[���[�B
�I�[�g�A�b�v�������֗��B
�����A��ɂ���ă_�X�g�J�o�[���q���W���_���ɂȂ��Ă��ďグ��Ȃ��Ɨ����Ă���B
���ꂪ���\�|���B
������KP-07�B
����̓~�j�`���A���f���ƌ������Ƃŕ����Ă�����Ƃ�ł��Ȃ��B
����Ӗ����[�J�[�����X�P���g���B���邢�̓l�C�L�b�hKP�B
�A�[�����ǂ����A�Ƃǂ߂ɕt���̃J�[�g���b�W���ǂ��B
�e�N�j�J��AT-E30�����i�ƌ�������̂ŁA�����AT-ML�Ɠ������̕��B
�����Ƃ����������������邩������Ȃ����A����Ȃ��̂��i���Ŕ����Ă����Ƃ����̂͐M�����Ȃ��B
������pro-ject��DEBUT3�B����ɂ��������B
�d���A�_�v�^�[�����A���얢�m�F���W�����N�����������̂�������͑��v���낤���A
����̏ꍇ��DC���[�^�[�����t���ēd�r�h���C�u���Ă��܂��A�Ǝv������
DENON MARATZ�ŃA�_�v�^�[�����o�����̂��f���ɂ�����g���Ă���B
���͂���DEBUT3�B�r����DC���[�^�[���d�l�ύX����Ă��āA�͂����A�_�v�^�[��AC��DC�^�C�v��
�v���[���[��炸�B
�ς��ȁA�Ǝv���ď�`������O�q�̃}�C�i�[�`�F���W�̂������ƕ������Č����ɉ����Ė�����̂�
��̎v���o���B
��������ăJ�[�g���b�W�A�I���g�t�H��2M������������A���ꂪ�ǂ����B
�C�R���C�U�[�������̕��ŁA����̓X���[���邱�Ƃ��o���Ȃ��̂����S����薳���B
�Ȃ�ł���ȗ��h�ȉ�������̂�������Ȃ��������{�f�B�[����������2024�N����̂��C�ɓ��肩������Ȃ��B
�Ō��TOA��DD-100�B
�����GW���h�t�c�A�[�Ŋm�ۂ��Ă������������N���炢�ҋ@�����Ă��܂����B
�A�[����JELCO��OEM�ł͂Ȃ����A�Ɖ\����Ă����̂�m���Ă�������ߊl�����̂���
�����Ƃ��̂������A�Ƃ��Ă������B
2024�N��KP-07�Ƃ�pro-jectDEBUT3�B������DD-100�ƁA��r�I���i��}�����v���[���[�B���������ꂽ�N�������B
���������������ʂ������炵���̂��H
�킩��Ȃ�������D�܂������Ǝv�����B
1��4��
2024�N�U�����������ŏI���B
�ߋ��L�����Ă������Ȃ�ĈӖ����������H�Ƃ����l����������̂���
�Ⴆ�����ƂɃC���f�b�N�X���U���Ă������āA�����Ă��̐l���ǂނ͍̂ŐV�̓��L�����Ǝv����
���܂ɂ��܂ƂߋL���������ėǂ��̂�������Ȃ��B
�Ō�̓A���v�ނȂǁB
STAX��SRA-12S�͂����Ǝ��グ��ׂ����Ȃ̂ɂ��߂�Ȃ����B
�v���A���v�Ƃ��Ă��D�G�Ȃ̂͑z���ɓ�Ȃ��B
�����Ă��̈���STAX���B�l�����n�����Ă��āA�B�l�̎�ɂ����PRO�o�C�A�X�ɂ��Ή��ɂȂ��Ă����肷��B
�����ɃC���[�X�s�[�J�[SR-404�������Ă��āA�����Ǝg���ׂ����낤�B���ȁB
�r�N�^�[JA-S41DC�BJT-V41�����������y�A�B
1977�N�ɋN����DC�A���v�u�[���B
���ł�����ł�DC�����ăo�����X��������Ƃ��������A����JA-S41�͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��Ă������H
�\�z�������āH�ƂĂ��ǂ����������B�F�C�͖���41�̕������邩������Ȃ��������Ƃ������邳�A
���Ă���41DC�̎������B
�J�Z�b�g�f�b�L�����o��B����͋v���Ԃ�B
�i�J�~�`480Z�͔�r�I�ȒP��������������TEAC C-3�͓�B
������ɂ��Ă����ȑO�Ɍ��Ă��Ă����Ƃ肷�鑶�݂Ȃ̂��J�Z�b�g�̖���Ȃ̂��Ǝ����B
�N�̐��ɃT���X�CEC-10�G���N���[�W���[�Əo����Ă��܂����̂��^�̐s���H
����A�����������}�nJA-3802�Ȃ�Ă���38�Z���`���j�b�g���������Ă����̂������Ȃ��������B
�����ڂ̑O���������Ă���̂����f�J���B
�����A�ӊO���W�F���g���ɖ��Ă���B�s�v�c���B
���邢�͈�Ԃ̕ω���������������Ȃ���d���̓����B
�C���i�[�T�b�V�̓y�A�K���X�Ȃ̂ŃK���X�̖����Ƃ��Ă��O���B
�����Ȃ�O�̉��͕������Ȃ��Ȃ����B
���̑剹���Đ��H
�c�O�Ȃ��炻��͎�ł͂Ȃ��B
�����A���_�����͑�ϗǂ��B
����������SN���͈�i�Əオ�����B
1��5��


�A���v��������ꂵ�炭�g�@�B

�����������j�����낷����������p����������̂��������Ƃ������̂���
�Ȃ�Ƃ����o���ɑ��������̂����߂Ė{�N����낵�����肢�������܂��B

����Ŋ����Ȃ�Ď��͂������Ȃ�38�Z���`3Way�Ȃ̂���
�Ȃ�Ƃ��`���[�~���O�ȉ��Ŗ�B
�����Ȃ�Ƃ��炭�͂��̂܂܂Łc�Ȃ�Ďv���Ă��܂��B
1��12��

����A�Q�����B
�����Ƃ������P�ł���B
���ꂱ����T�����炢�~�܂�Ȃ��B
���łɕ@���l�܂�B�M�͏o�Ȃ��B
����Ȃ���ȂŁA������A������[�̕����A�̔����J��������炸�B
�܂����������Ȃ��̂������������ɂ������B
���āA�摜���u���Ƌ��ɋ���ʁv�B
���܂��܍����e���r�ł���Ă����B
��������ς��͍��ł���A�a�g�̂ł͓�����Ă����Ȃ��B
�r���r�����E���ς��Ă������A�܂��s���Ȑl���ł���B
��r���Ă킪�l���́A�Ȃ�����}�Ȃ��Ƃ�c
�����������A����ŗǂ��̂��ȁH�Ƃ��v���B
�����蔲���Đ�����A�Ƃ����̂̓h���}�ɂ͗ǂ���������Ȃ���
�}�f�̐l���ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��B
�}�l�̖}�l�ɂ���I�[�f�B�I���L�����܂ł��Ə����c
����A��ꂽ�c
1��13��
�ǂ���炻���ȒP�ɂ��������Ȃ��ƌ�����B
�܂��A��������ɐQ�Ă��Ă����������P�͏o�₷���Ƃ��킩�����B
�c�Ȃ̂������炢�܂ł͏o�ĉ߂������B
���̕������������݂������B
�����Ă���ƃI�[�f�B�I�̂��镔���ցB
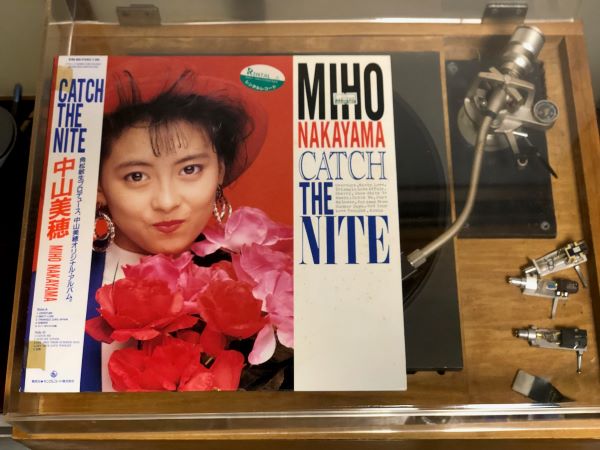
�m�������ꖇ���炢�������c�Ǝv���������ς肠�����B
�P�X�W�W�N�Q��������6th�A���o���B
���������ăA�i���O�ŏI���H�Ȃ�Ďv�����炻��Ȃ��Ƃ͖��������B
�l�C�����邩��ǂ�ǂ�o�Ă����̂��ȁB
���Ă��������̃A���o���B�܂��W���P�b�g�͌l�I�ɂ́u�ǂ��Ȃ́H�v���Ċ����B
�܁A�]�v�Ȃ����b���낤���B
�������^���B
����͋v�X�ɖ��키�s���^���B
������[�̕����͑����̃\�t�g�������ł���悤�ȕ����ɐU���Ă��邪�A
����ł��炪�����邩���X�S�C�B
�܁A���ꂱ���傫�Ȃ����b�Ƃ������̂��B
�����̐l���c�т��������̂ł��낤�B
���̈Ӗ��ɂ����Ē��R����͂�����[���ꉭ�{�G���C�B
���A���ꂩ�炱�̔Ղ̓����^�������ł����B
1988�Ƃ����ƁA�܂��A�i���O�����^�����ăe�[�v�ɗ��Ƃ��Ȃ�Ă��Ƃ�
�s���Ă����̂�������Ȃ��B
1��14��
�I�[�f�B�I�Ƃ����̂���G�c�Ȑl�ɂ͌����Ȃ���
�ׂ��߂���l�ɂ������Ă��Ȃ��A�ƌ������̂͒����搶���������낤���B
�K���ɑg�ݏグ���X�s�[�J�[�̉��Ȃ����Ă����
�^�S�ËS�ɂȂ��ē��R�B�Ȃ�Ȃ��������������H
�����Ȃ�Ƃ��ꂱ��M�肽���Ƃ������A
�M���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂���܂����H�Ƃ���
�ςȏՓ��ɋ����B
�Ȃ̂����A�������N��̐�����ƂƂ������A�݂̂����ɂ�
�����オ���Ȃ��B
�ډ��C�ɂȂ�̂́A���̍�������������̕�����
������ʂ��Ă���悤�Ȋ��o�����邱�ƁB
����A�w��L���Ē����ςޒ��x�Ȃ̂���
���͏C�s�m�ł͂Ȃ��̂ł���B
��ԗǂ������Ȃ͈̂֎q�i���삾�j���������������������邱�ƁB
����������Ȏ��Ŗ{���ɗǂ��̂��낤���H�ƔY�ނ�����
���͉�����̂ł���B
1��15��
�ǂ���1/15�����l���łȂ��Ƃ����̂�
���q�������B
�c���āA���肳��Ă���l�����I���炢�߂��Ă���̂��c
�b���͕ς��A�����������ʒu���������ė����B
�ǂ������ǂ������c
���������H
����A���ɂ�����Ȃ��̂����c�C�[�^�[�i�R���v���b�V�����h���C�o�[�j��
�g���R���f���T�[�����l��������B
����܂ł�3,3��F�������̂�1��F�ցB
���ꂾ���ł���B
3,3���Ɖ��w���c�N���X�ɂȂ�̂��͒m��Ȃ���
1�ɕς���ƁA����܂ł����������g���ł̃N���X�ɂȂ邭�炢�͂킩��B
�ȒP�Ɍ����Ă��܂��ƁA����܂��̓c�C�[�^�[���������߂��Ă����A�Ƃ������Ƃ��B
����̏ꂪ�������Ɍ��肳�ꂽ���ƂŃE�[�t�@�[���o�����o�����B
����ɂ���ăc�C�[�^�[�Q�ƃE�[�t�@�[�̏�[���������炢��
�{�[�J�������������悤�ɂȂ����Ƃ�
�R�̗l�����{�����B
�����ăX�s�[�J�[�r���_�[�̕��B�Ȃ�
��L�̐�����ǂ���������邱�Ƃ��낤�B
�u�R�C�c�n�@�I�[�f�B�I���i���N�����āH�v�ƁB
��荇�����v����������g�킸�A���������𗊂�ɉ������ƂȂ��
����Ȃ����Ɩl�͎v�������_�͂�����Ȃ��B
�g�����p�[�c�Ȃ�Ă̂���R����Əo���鎖�͑����邱�Ƃ��낤�B
�F�X�Ȑ��l�̃R���f���T�[�B���邢�̓R�C���ɒ�R�B
�A�b�e�l�[�^�[�����Ċ܂܂�邩�B
���������`�����f�o���������������Ղ��Ƃ��F�X���B
�����A���Ȃ��Ƃ����͐g�̉��������Ă��镨�ł�낤�ƌ��߂Ă���B
�Ȃ����āA�L�����Ȃ���������Ȃ��Ȃ�̂����������炾�B
���悢��s���l����������o�������ł���B
����Ȋ����ŗǂ��Ǝv���Ă���B
���āA�P������ɂȂ�Əo�Ă���c
���̂�������ł͂Ȃ����A���i���̂��ԋp����
�e�����o�Ă�����Ƃ����ɂ��F�X������B
���̏��������l���\���グ�܂��c
���߂�Ȃ����B
1��16��

���悢��A�Ƃ�����ł��Ȃ����R�W�Z���`�E�[�t�@�[���̂�����
�Λ����鎞�������̂��H
����A�܂������Ɩڂ��Ԃ��Ă����̂����c
���邢���ő����肩������Ȃ��B
����͒ቹ�s���ł���B
�i�����͂܂��B��ꂿ������c�j
1���P�V��
�R�W�Z���`�E�[�t�@�[��i���Ēቹ�s���Ƃ͂��悢��
�������������H
�������ɒቹ���S�R�o�Ă��Ȃ����J���J�����������Ƃ�
����Ȃ��Ƃ������B
�����A�u���ꂪ����a�E�[�t�@�[���I�v�Ƃ���
���ōU�߂Ă���悤�����͂Ƃ��������͂ɂ������������B
���͂���͐��̒��ɂ͂悭���鎖���B
�R�W�Z���`�Œቹ�s���H
�ł������ꔭ�R�W�Z���`��ς���_�u���E�[�t�@�[�Łc
�ĊO�������Ȃ������肷��c
����ň���ȒP�ȉ�����B
����͍Đ����ʂ������邱�Ƃ�������Ȃ��B
�����A����͂�肽���Ȃ��Ƃ������������I���B
���ɊȒP�Ȃ̂��d�C�I��B
�p���C�R���g���Ă̒����B
���̏ꍇ�o�C�A���v�ɂȂ邪�d���Ȃ��̂��B
��́c
1���Q�O��
�ቹ�s���H
����Ȃ����Ȃ��ł���A�Ɖs���w�E��S������������炢���Ղ����B
�s���I
�����P�Ȃ銨�Ⴂ�ł��낤�B
����ł��c

����Ȃ��Ƃ����ĕω����m�F���Ă݂悤�Ƃ����肵���B
�_�N�g�Ɏ��܂��Ă���̂��g�C���b�g�y�[�p�[�ł���B
���ꂶ�Ⴀ�����킩��Ȃ��H
������������Ȃ��B

�ʂ̐�����v�������B
�G�b�W���d�����Ă��邩������Ȃ��B
����A�܂����G�I�ɂ͂���������̂����c
����ɂ��Ă����̃|�����C�g�A�������B
��̂��̂��H�H

��荇���M�œh���Ă݂邱�Ƃɂ����B
1��21��
�|�����C�g�Ō��ʂ�����̂��ǂ�������Ȃ����A
���������G�b�W�����Ă���悤�ɂ��v���Ȃ��B
�����A��������p�������Ǝv����̂Ȃ玎���Ă݂������ł��傤�B
�����o���āA�u�����`�ቹ����������o�ė��ċ����Ă��܂��v
�Ƃ����̂������B
�Ƃ������l�̊S���ቹ��������Ă��܂����i�Ȃ�č����z�I�j�̂�������Ȃ��B
���̊ԈႢ���A���̂܂Ƃ܂肪�Ƃ��Ă������Ȃ����悤��
������͉̂��́H
�v�������������Ȃ̂����A�܂��G�b�W�̏�Ԃɕω����N�����
���ɉ��炩�̕ω��͋N����Ƃ������ƂȂ̂��B
�����悭�킩��Ȃ��B
�����葼�ɋC�ɂȂ�Ƃ��낪�o�n�߂āc
1���Q�Q��
�C�ɂȂ�c
�����H
����A�����{�[�J����������������~�����Ƃ������c
�݂����Ȋ����ŁA�ق�ˁA����Ȏ��n�߂���D���Ȃ̂�B
�t�ɂ����Ƒ��̗v�f�����������Ă������Ď��Ȃ�ł����ǁB
���ɐl�Ԃ̗~�ɂ̓L�����Ȃ��c
�ƁA�����Ă��Ă��d���Ȃ�����c�C�[�^�[�i�R���v���b�V�����h���C�o�[�j��
�R���f���T�[�����B
�e�ʂ�1��F�ł��̂܂܂Ȃ̂����o�C�|�[����
�d���R���f���T�[�����]�����t�B���������B
�����A���͕ς��̂��c�H
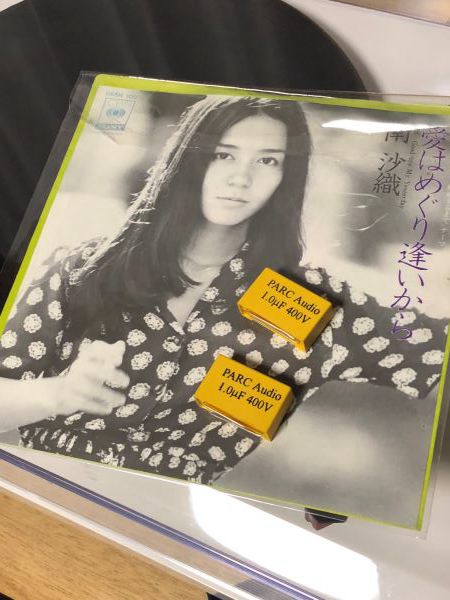
1���Q�R��
PARC Audio�ł���B
�ƌ����Ă��ǂ��͒m��Ȃ��B
���͎莝�������r�R���@�t�B������1��F��T���̂���
���ꂾ�������̂��s���s���ŒT���̂ɔ��ʂĂĂ��܂����̂������B
������Amazon���]���̗ǂ��t�B�����Ƃ������������ȗ��R��
��������`���C�X�B
���F���Ďl�p���Ƃ����A�ߔN�F�X�ȂƂ���Ō�������X�^�C���ł���B
���Ă��������ł���B
�����������Ȃ����B
�����C�̂����ł��Ȃ��B
���͊m���ɉ��P����Ă���̂����A���܂���P���߂���
�����ėǂ����ǂ����������B
���������ω��������Ə����Ċ�Ԃ̂������
��������v�Ƃ������́B
����ł��炭�炵����A�����R���f���T�[�ɖ߂�����
���͗ǂ��܂܂������Ƃ��F�X�N����̂��I�[�f�B�I�Ȃ̂ł���B
��荇���������Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ���B
���ɓI�Ɏv���邩������Ȃ����A���ꂭ�炢�ŗǂ��B
1���Q�T��
�ǂ��ɂ������Ȃ��B
�Ȃ�ď����Ƃ��a�C�ł����H�ƌ���ꂻ�����������ł͂Ȃ��B
�Ȃ�Ƃ������A�P�Ȃ��̗͒ቺ�ł���B
�u������ˁv�Ƃ�����[�����ɘb������A
�u�d���Ȃ��̂�A�T�O�߂��������]����A�]���v�ƌ����ăn�b�Ƃ����B
�����ȂA�]���ȂB
�����ł����������Ă�������Ȃ����B
���͂�����Ă��邾��������̂悤�Ȃ��̂��B
�l�����{�[�i�X�^�[���B
�锪���܂ŋN���Ă���ꂽ���������́B
�����v������v�w�ł����Q�Ă��܂����B
�t��������I�[�f�B�I���L���Q�U�N���ɓ���B
�Q�U�N�O�ƍ��ƁA�����悤�œ����ł��Ȃ��̂ł���B

�ȏ�̘b���ƊW�Ȃ��A������Ƃ̂���肪����������
�I���g�t�H������r�I���[�R�X�g�̃J�[�g���b�W����������o���Ă���B
VMS�A�ł͂Ȃ���F15O�Ƃ����V���[�Y�B
����Œ����A���w���̎��ɔ����Ă���������R�[�h��
�\���ǂ����Ȃ̂��B
�I�[�f�B�I�����{�����f���炵���c
1���Q�U��

�����ăW���e�b�NV-�V
����ς�V3�����ʃ��C�_�[���낤�A�Ɠ˂����݂����Ȃ邪
����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悢�B
���̃J�[�g���b�W���j��`�b�v���ʖڂɂȂ��Ă��镨����ɓ����
MT-23���Ȃ̃J���`���o�[���������������}�����Ƃ���
�����܂�́H�p�^�[���̂ЂƂ��B
���̎��͂�������J�T�J�T���������̉��Ɏv���āA
��������ς菃���j����Ȃ����ʖ����ȁH�Ȃ�Ďv�����̂������B
����v���Ԃ�Ɉ�������o�����炻��Ȃ��Ƃ͖����B
����͔@���ɁH
�����j�����Ǝv���B
�����2g���|������B
����ł��̌̂͗ǂ��̂��낤�B
�ق�̋͂��ɑ@�ׂ���������Ƃ��낪����C�����邪
������������V�F���̂������ȁH�Ƃ��v�����肷��B
�ŁA�܂�����ȕ��ɂ��ꂱ�ꕷ����ׂ��肵��
�����������o�邩�ǂ����A�Ȃ�ĂƂ���ŃX�s�[�J�[��
��ԁi�o����j���m�F�����肵�Ă���B
1��27��

�܂Ƃ��ȃo�����X��38�Z���`�͖��Ă���Ǝv�������̂���
���ׂ̈ɂ���r�Ώۂ��K�v�B
���͂��̖���AST-S1���S���Ă���Ă���B
�Ƃ�������������v���Ԃ�ɒ����Ă݂��B
�����̂������������������B
������O����������~�j�`���A�̐��E�Ȃ̂��B
�����ቹ�Đ��Ƃ��������ł�AST�̉��͋C�ɓ����Ă���̂���
�h�y���h�̂��B
�������A����ς�N�\�ł����G���N���[�W���[�ɂ��Ӗ��͂������̂��A��
�ςȂƂ�������S���Ă��܂����B
1��28��

�����B���X�e�b�v�B
1��29��
�����B���邢�͋��l�̂��킲�ƕҁB
�ʐ^�������Ƃ킩��ɂ����Ǝv�����A�v������Е���G7�ɂ��Ă݂��B
������G7�̃c�C�[�^�[�͔����āA�g���Ă���̂̓E�[�t�@�[�ƃX�R�[�J�[�B
�����ď���R���v���b�V�����h���C�o�[�ƍX��0506mk2���A�����38�Z���`�̔��̏�ɍڂ��Ă�������
���̂܂��ړ������B
�ӂ�����ȁH�͂��A�ӂ����Ă��܂��B
�Ƃ��낪���ꂪ�}�b�`���Ă���H���͂����̐��E�ł���B
�����������B�ŏ�����}�b�`����Ǝv���Ă����B
�������M�͂ǂ����痈���H
�P�Ȃ����Ă������ł���B
�Ȃ�ł������������\�N�Ɣn��������Ă���Ɛg�ɕt����������̂���B
�ŐH��ΎM�܂łƂ������Ƃ��Е���38�Z���`�i�G���N���[�W���[EC10)�̂܂��ŃX�e���I�Ŗ炷�B
�ܘ_�܂Ƃ��Ȏg�����ł͂Ȃ��B
�Ƃ��낪���E�Ŕ\�����Ƃ����F�����Ȃ葵���Ă���̂ł���B
��������ɂ͈قȂ�̂����꒮�đR���D���Ƃ����̂������B
�ƂȂ�ƁA���B�ǂ�����c�����H�Ƃ������ɍs�������킯�ł���B
���������Ȃ̂���G7�̕����R���p�N�g�ŁA���̓_�L���ł���B�Ӗ�������������u���Ă����K�v�͂Ȃ��B
1��30��
������G7�~2��g���ɁB�܂�܂Ƃ��Ȏg�����ɁB
������G7���c�C�[�^�[���O����A�V�ɃR���v���b�V�����h���C�o�[�{0506���������Ă���B
�l�b�g���[�N�ł���Ƃ��A�b�e�l�[�^�[�Ƃ���EC-10+JA3802�̏�ɍڂ��Ă��������S�������ł���B
�V�̏�ɍڂ����c�C�[�^�[�Q�����̍����ɍ����悤�ɂƁAG7�����ɒ��u���Ƃ���B
���̎g�����̓x�X�g�Ƃ͌����Ȃ�����荇�����ł���B���������w����EC-10�G���N���[�W���[��������
G7�͂��̑O�ɒu����邩�烊�X�j���O�|�C���g����̋�����1,5���[�^�[���炢�Ƃ��������߂�����B

���̏�ԂŊ���̃\�t�g�����A�u���������ǎs�̂̃X�s�[�J�[���ėǂ��o���Ă��܂��ˁv�Ƃ���
������O�̏��ɍs��������B
�ǂ��Ӗ����G���K���g�Ȃ̂ł���B�R���v���b�V�����h���C�o�[�{0506���ǂ����t���ɂȂ��Ă��邪
�g�[�^���̉����s�v�c��G7�̉����̂����Ȃ̂��B
�ۗ������Ⴂ�����������̂��u���̎q�͂������v����R��KICC211���B

�����搶�ӔN�̐����Ղ̂ЂƂʼnԉ���t����̃s�A�m���o�b�N�ɗ��삳�z���ɉ̂��V���v���^������
���ꂪ�������₩�ɐL�ѐL�тƖ�B
����[�A�Q�����ȁA�Ƃ��������B
�������Č��ɖ߂�܂����A�Ƃ������Ƃ��B
1��31��
�f7���^���݂����ɂȂ肻�������A���܂ł�����ŗǂ��̂��ȁH�Ƃ����C�͂��Ă���B
�ǂ��X�s�[�J�[�����n�C�G���h�ł��Ȃ����낤�Ǝv���B
�����n�C�G���h�X�s�[�J�[�Ƃ�炪�~�����̂��Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B
�D�ꂽ�X�s�[�J�[�͂���̂��낤���A�ߔN�͐V�����̂��Â��̂������Ȃ��߂��ł���B
�I�[�f�B�I�Ȃ�Ă̂͂���قǂ̕������Ȃ��Ə�X�v���Ă��邩�琴���̕��䂩���ԋC�����ȂS�R�����B
�����Č�����G7������ɓ�����G9�ɂ͋����������Ă���B���������Ƃ����������ꂱ��ł���킯�ł��Ȃ���
���a�I�[�f�B�I�{���Ƃ��Ă͓K�ȃ`���C�X���Ǝv���B
�����AG9�ӂ�������Ȃ��߂��ł���B
�Ⴄ�����Ƃ���P-610�{�c�C�[�^�[��2Way�Ȃ�Ă̂�����B
���ɂ�������邪�����Ēu�����B

�����͂�����ł�
��O�̓��L�ɖ߂�
���L��MENU��
�\����