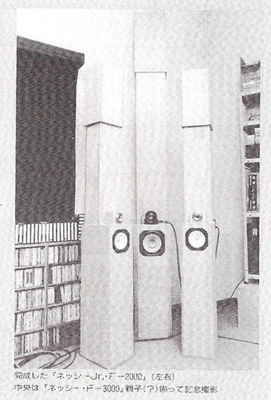|
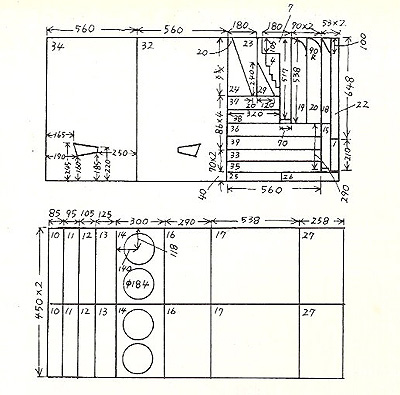



D-70以降音道の設計が変わり、長岡式BHの奥行きは深くなった。 それ以前のD-7系は今思うとコンパクトと言っても良い。 D-7系からD-70系への転身。そのメリットは? 一つは音道が直角の折り返しで作られているので 製作する際に曖昧さが無いということ。 D-7系は内部の仕切り板が斜め、斜めの連続だし 工作上曖昧さが残るところがある。 これを一掃出来たという点でD-70系の功績は大きい。 しかし引き替えに巨大になったのはいかがなものかと 今は思う。 D-7系は案外小さいし作りもシンプル。 必要とする合板の枚数も実に少ない。 D-7MK2は21㎜厚合板4枚で二本作れる。 これに対してD-58なんかは倍くらい使う。 D-7をスレンダーと呼べばD-5X系はハイファットと 言っても良さそうだ。 悪い事ではないのだがD-7、D-70、D-5X系と進むに連れて 全体に物量投入型となっていく。 どうだ!と見栄を張るには凄いユニットや大量の合板が 使われている方が良いのだろうが、 シンプル、スリムを愛する人はいまだにD-7系を捨てきれないで いる。(心情的に、だ) そのせいだろうか、約10年前に出た長岡先生のムック本 「観音力」では人気投票でしっかり第六位にD-7MK2が 入っている。
なんだかD-70やD-55以降のBHを非難している様に 受け取られかねない様な事を書いているが そんなつもりは毛頭無い。 D-70なんか未だに僕の憧れるBHの第一位だ。 あのルックスは素晴らしい。 ただ単に少ない合板や限定でもなんでもないユニットで 作れるD-7系をここでは贔屓にしているだけ。 それと話しの原点に戻って、そのコンパクトさが良いというお話し。

となると結局16㎝ユニット採用の物になる。 例えばFE-168SS×2発用のD-66なんか 往年のD-7を偲ばせるプロポーションとなっている。
D-66よりも先に開発されている。 幅24㎝、高さ100㎝、そして奥行き45㎝と正に理想的プロポーション。 傍に立っている長岡先生ご自身がどちらかというと 小柄な方だったので、D-37のコンパクトさも良くわかる。 これぞ日本の平均的家屋向けのサイズだと信じる。 六半に始まり六半に終わるというが 16㎝ユニットはやっぱり一つの理想なのかもしれない。 しかし長岡スピーカーでは16センチはちょっとマイナーな存在。 正確に調べたわけではもちろん無いが、20㎝、10㎝の製作例 と比較するとかなり少ない筈だ。 やはり大きく行きたい人は20センチを選んでしまうだろうし、 小型を作りたい人は10㎝、8㎝とより小さい方へ行く。 かく言う僕自身が20㎝、10㎝、8センチはせっせと作ったが 16センチは作っていない。これが現実だ。
実際には却って手を出して貰えない、 バイクで言うなら中間排気量車みたいなものか? 350CC、あるいは550CCあたりがベストかもと思いつつ どうしても400、750、あるいはリッターバイクと 少しづつ大きい方を選んでしまう。 あるいはいっそ125、50と行ってしまう訳で 人間の決断というのは、そうそう理屈通りには行っていない事がわかる。
おっと、そもそも最近の日記は 「長岡鉄男最新スピーカークラフト3 バックロードの傑作」に関するものだった… 大分逸脱している? ところで当該単行本に収録されている21機種を眺めても 16㎝を採用しているのは一機種しかない。 その一機種はF-2000。すなわちネッシーJrだ。 本家F-3000は方舟のリファレンス。 当初のコンセプトは20㎝+ツイーターで16Hz~40kHzの超ワイドレンジ 再生を目指すというもの。 長岡鉄男を好きな人も嫌いな人も居てそれでよいが、 氏の残したものはやはり色々あって興味深い。 その一つにこの共鳴管スピーカーというのがある。 もちろん共鳴管スピーカーは市販の物にもあったが 真っ正面から挑んだのは長岡先生の方。 というかメーカーとしてはやばすぎて手を出せない形 =超トールボーイで実現させた。
というと、バックロードホーンがあり、マトリックススピーカーがある。 またダブルバスレフも忘れられない。 一連のアプローチの中でも共鳴管は晩年期のものと言っても良い。 1980年代が終わる頃に手がけられた。 最初は共鳴管一本では癖が付くのでは?ということで 複数管使用のカテドラル。 これがまず成功。 続いて共鳴管一本。ユニット二つのコーナー型、カノンが成功。 いよいよ本格的にということでネッシーの前身とも言える ハイカノン(20㎝一発+ツイーター)に至り方舟最初のスピーカーとなる。 先生の言葉通りだが、共鳴管、音響迷路、バックロードは 地続きであり、単純に分けるのは難しい。 共鳴管はバックロードと似た要素も持つが やはりホーンではないから別物。 むしろ音響迷路的要素の方が強いが 迷路が音道の折り返し数をある程度増やすことで 癖が強く出るのを防ぐのに対して 折り返し数を原則一回程度までとした共鳴管は むしろ開き直って“癖も音の内”と言い切っている感じもある。
別な視点で見ると以上三つの内、共鳴管のみが 超スリムタイプを設計できる物と言うことを忘れてはいけないと思う。 というか、共鳴管はスリムにならざるを得ない。 折り返し数が多すぎると音響迷路になってしまい 癖も半減するが肝心の共振効果も減ってしまう。 だから長岡先生設計の共鳴管はのきなみスリムなトールボーイ。 占有床面積は250×250程度から300×350程度である。 これは今月の日記で重要視している“大きさ”という観点からすると 非常に好ましいものということになる。 実はよっしーがD-55もスーパースワンも投げ出して ネッシーを作ったのはこの占有床面積の点に強く惹かれたからなのだ。 (単純)
ユニット構成は同一なのに 床に対する大きさは片や444×560。 片や300×345と大分違う。 これは大変結構な事である。 ただし、物事全て一長一短。 スリムは良いが背の高い分ふらつきは出やすい。 超トールボーイをふらつき無く設置する。 これは案外難しい。 安定という点ではD-55やスーパースワンの方が遙によい。 ネッシーはフラフラだ。 これが音に影響しない筈がないと散々悩んだ。 結果をいうと、僕の場合は天井いっぱいの高さで作り 共鳴管トップと天井の間にくさび(と言っても100均で売ってた 硬質ゴムのドアストッパーだけど)を何ヶ所か叩き込んで ようやくふらつきを止めたわけだ。

最初のカノンしかりだしその後の一連の作品もそうだ。 特に初代カノン、及びビックカノンはユニットを90°配置で二つ 持っていて、コーナー設置の音場型的要素を色濃く持っている。 もうひとつ。コーナー設置には別の意味もある。 共鳴管スピーカーの低音はダラ下がりにどこまでも伸びるが 量としては不足する場合が多い。 何故かというと共鳴管を制御するために ある程度強力な磁気回路を持ったユニットを使わざるを得ないからだ。 これは一種の二律背反とも言えるが仕方ない。 結局はバランスの問題ということになるが 強力型ユニットを採用すると低音ダラ下がりになるのは避けがたい。 要はこれを何らかの形で補強してやれば良いわけで、 そのためにはトーンコントロールの使用とか マルチアンプでサブウーファー使用とか色々あるのだが コーナー設置によるルームアコースティック効果で 低音を持ち上げるというのも一つの解決策。 実際「バックロードの傑作」に納められているネッシーJrの項を 読むとわかるが、コーナーを上手く利用することで 低域はグンッと持ち上がってくる。 ただ、今度は逆に、そう設置に都合の良いコーナーがあるか? という問題に直面する。 もう一つ。コーナー、あるいは後の壁を利用するシステムというのは その壁や天井の材質等の影響を強く受けてしまうという問題もある。 更に、これを言ってはおしまいかもしれないが コーナーに押し込まれた時の音を気に入るかどうか?という点も問題だ。 と、色々あるが、それでも共鳴管の音に興味を持ち セッティングのメリットデメリット共に付き合ってみようと思える人には この方式やっぱり興味深い物だと言える。
一つ前の日記に戻る 日記のMENUへ 表紙へ
|