|

自覚はしている。 しかし、今回防音室内で起きた事は 文章で説明しようとすればするほど 疑われてしまいそうな感じだ。 僕自身、嘘かと思って日を改めて音を確認したりもしているのだが どうやら嘘や偶然、あるいはまぐれではなかったようだ。 何というか大変結構な音がしている。 いや、大変結構な…などと覚めた風を装ってはいるが 正直嬉しくて仕方ないのだ。 だって、こんなに上手くいっちゃうなんて…(笑)
僕の中では一つの完璧なのである。 どう“良い”のか? ①まずジャンルを選ばない。 何だって来い、なのだ。 実は…、そんな事を言える装置を組みたいな と思って足掛け30年は掛かっているのだから これはもう一つの成就をしたようなものではないか。 クラッシックOK、JAZZもOK。 そしていわゆるポピュラーやROCKだってOK。 正直言って、自宅のロジャース君は ROCKなんか苦手だ。 教室の防音室外を担うコンコルド君は 何だってOKだけど、何だってそこそことも言える。 こんなに何でも上手い具合に鳴ってしまう装置が 現れるなんて夢にも思わなかった。 というか半ば諦めていたというのが正直なところか。 おっかさん、よっしーは遂にやったよ!(←馬鹿…) (続く)
さて、続きです。 ②レンジは極めて広い。 極めて…を付けて良いかどうか? 多少疑問の残るところ。 そりゃこれより広い物と比べれば、狭いということにもなろうが そこはそれ、あくまでも主観に基づいてということで。 でも、広い。 高い方は爽やかに伸びきっている。 これについては月並みだけどHMA-9500の貢献があるかも。 なんというか、スーパーツイーター要らず みたいなアンプなんです。 そして低い方。 これが貴方、結構に伸びているから驚くではありませんか。 それでいてブーミーではない。 これはもう謎としか言いようがない。 このスピーカーはYSTスピーカーなので 本来は専用アンプでドライブするのが筋? しかし、論より何とかで、PRA-2000+HMA-9500で 確かにまともな音がしているのだから仕方ない?
初めて思ったのは遙か15年くらい前になる。 なんでそんな事を思ったのかというと とあるデザイナーさんの事務所で そのような事をしている実例を見たことがあるからなのだ。 アンプはラックスの管球式で、確かセパレートだったと思う。 CDプレーヤーは思い出せないし 別に音を拝聴したわけではないのだが とにかくご職業柄か格好良く並べられているのに 感心したものだ。 その時、“YSTスピーカーって専用アンプで無くても OKなのね?”と思った次第。 いや、音を聴いた訳でも何でもないのだからOKだったかどうか 判断のしようもない。 ただ、その時そう思った事が 後にティファニーのスピーカーを拾ってみようという 気になるきっかけだったというお話。

結果的にとっても上手く鳴っているのだから仕方ない。 バスレフが実に上手く動作しているな、という感じで ちょっと前に弄っていたP-610段ボールとは偉い違い …って当たり前か。あれはちょっと冗談が過ぎた。 うまく行かなかったのはP-610のせいでないのは 言うまでもない。 ソフトによっては低い方にアクセントが付きすぎるが それはソフトのバランスがそのまま出てきているのが 他のソフト(自分にとって物差しとなっているようなソフト。 色々な環境で散々聴いて特性を掴んでいるソフトの事) と比べてみると良くわかる。 ま、とにかくこのスピーカーから出ている音とは 俄に信じがたい感じの音がする。 …と褒めちぎったが さすがに何の問題も感じないと言うと嘘になる。 例えば…。 (続く)
…といっても気になる所というのも あるような無いような…。 敢えて言えば「みどりアンコール!」みたいな 難物ソフトでちょっとくじける所があるくらいか。 まあこれも一回トライしただけなので 日を改めてやってみるとクリアー出来るかもしれない。

クリアーしている。 ただ、極めて録音の悪いソフトに関しては やっぱり駄目である。 これは当然の事だけど…。 後は大変結構。 「タイタニック」の超低音も問題なし。 何か間違っているのでは?と思いたくもなるが 事実は事実だから仕方ない。 それより目下一番の問題は この部屋に立ち寄ると時間の経過を忘れてしまうこと。 ただでさえ早くはない帰宅が余計遅れる。 これはちょっとまずい。 それと首が痛くなる。 というのも、今のところは音場が上方に展開するため ついついそちらを見上げてしまうからだ(笑) 本当に首が痛くなってきた。 これには対策が二つある。 一つは本を持ち込んで読書をしながら聴くこと。 当然首は下を向く。 そしてもう一つは立って聴くこと。 これがまた立ったら立ったで音のピントが一段と 合うのでドキドキものである。 耳が天井に近づいて、音に癖がつくかと心配したが それもない。 ただ、当然脚が疲れる。 あんまり不自然な事はするもんじゃないと反省した。
次はYSTのおさらいとアビテックス(防音室)の おさらい。 この結果の謎に挑戦?
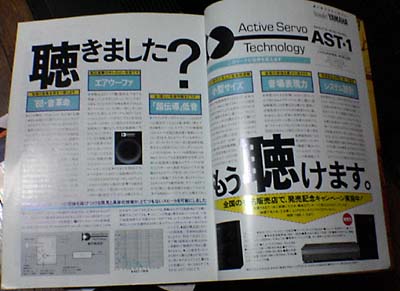
余所様のサイトとは偉い違いだといつも恥じている。 さて、YST。 元々はAST(ActiveServoTechnology)と言っていた。 写真はその技術を応用した最初の製品 AST-1の広告でAVFRONT創刊号から。 ’88音革命と書かれているので一目瞭然だが 1988年のデビューである。 特許46件出願中。二つの理論を結びつける発見と具体化技術が とてつもないスピーカーを可能にしました、と書かれていて 当時の意気込みが伝わってくる。 46件の出願中の特許が何かはわからないが 二つの理論については説明出来る。
これはキャビネットとポートの大きさを適切に設定すると 小型キャビネットでも与えられた小さな低域振動を 大きな音としてポートから取り出す事が出来る、というもの。 これは従来から言われている事だが 問題は理論その2の方。 スピーカーユニットの低域振動に限界があるのは ボイスコイルがインピーダンスを持つためで これを打ち消す事が出来ればユニットは振幅は小さくても 超低域まで正確に振動することが出来る、とされている。 ASTはもちろんバスレフ形式が基本になっている。 バスレフとはダクトをスピーカーユニットで共振させるものとも 言えるのだが、共振を起こりやすくさせるには ユニットの振動板がふらふら動かないように固定してしまう (本当の固定ではなくて動きにくくさせるという意味) 必要がある。 それには二つの方法があって、一つはユニットの磁気回路を徹底強化して ダンピングファクターを大きくすること。 そしてもう一つがアンプ側に工夫をしてユニットのインピーダンスを 見かけ上ゼロにしてしまうという方法だ。 (長岡先生のご著書を参考にさせて頂きました) ASTはもちろん後者。 AST-1の広告では、“アンプによる負性インピーダンスドライブ” という言葉が使われている。 (続く)
奇しくもAST(後にYSTと名称変更)の 登場はAVFRONTの創刊と同時。 因縁めいたものを感じるが お陰で結構詳しい開発秘話なども読むことが出来る。 ’89年5月の実質創刊3号で麻倉怜士先生がコラムで 取り上げていらっしゃるが、 それによれば考案者のヤマハ横山事業部長が 「カンターテドミノ」のトラック6のノイズ(30Hz付近なのだが 教会の外を通る車の排気音が入ってしまっている) を再生出来ず、 悔しい気持ちのまま夕飯を摂っていると 往来を通るトラックのノイズが気に障った。 ここでマフラーと低音の関連性に思い当たる。 翌日訪れた先は同じヤマハでも発動機の方。 そこにはマフラーの音の制御に関する膨大なノウハウがある。 当たり前といえば当たり前なのだが…。 更に、たまたま横山事業部長はその時カーステレオ用に MFB(モーショナルフィードバック)の研究をしていた。 そこでMFBスピーカーとマフラーを組み合わせてみたら 凄い低音が出た。 とっくに特許が出ていると思われた、このMFB+マフラーなのだが 何と一件も出ていなかった…。 正に偶然の連鎖でASTは世に出たのだが 実際の商品開発でもポートのノイズの抑制に管楽器部門の知恵が 注がれたりとか、さらにヤマハスポーツから ゴルフクラブの設計の為に使う高速度カメラを借りることが出来て 風切り音の研究が出来たりとか これはもうYAMAHAグループだったからこそ ASTは世に出たのね、としか思えないお話が紹介されている。
YSTは進化して生き続けている訳だから これは立派な“発明”であったと言って良いだろう。 さて、しかし専用アンプを通さないASTスピーカーの音って…? ボーボー言ってしまってお話にならないのでは? という想像は今回の場合軽く一蹴されてしまった。 何度も聞き返すのだが、実にまともな低音が PRA-2000+HMA-9500+ASTスピーカーから出ている。 それは貴方の耳がおかしいからよ、と言われても仕方ないが 論よりなんとかだから仕方ない。 量感良し、伸び良し、制動良し? 間違ってもブヨブヨしただらしない低音ではない。 いや、それどころかトータルではかなりソリッドな 超低音が得られている。 疑われても仕方ない。 なんて言ったって、誰よりも僕自身が 最も首を傾げている。 まあ部屋との相性が良かったという事にしておこう? (次はそのお部屋のお話)

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。
|