|
とても寝苦しい。 とうとう起きてしまいこれを書いているのは28日の3時半(笑) さてと…

元々そうするつもりだったので。 何しろ段ボール。軽いです。持ち運び自在。 写真のようなセッティングでいきなり音出し。 スピーカー台が椅子というところがお茶目だけど 考えてみれば昔はみんなこんな感じだった。
僕はシステムを更新したりした時に最初に聴くCDは これだ、とか決めて取り掛かるような繊細さはは全く持ち合わせていない。 だからこの日もたまたまCDP-777ESAに入ったままになっていた(笑) カーペンターズのベストが勝手に掛かったのをそのまま聴いた。 が、これがなかなかの物だったので正直驚いた。 フワッと音が広がるし見通しも結構。 普段は何気なく聞き流してしまう (というか音楽その物に浸ってしまう) カーペンターズなのだが エンジニアの音作りというか狙いというかが かなりはっきりわかるような気がして興味深かった。
JA-S71。 今回もほぼ迷わずラウドネスコントロールをONにした(笑) ボリューム位置は9時くらいで充分な音量になる。 この場所は確かに広い(正味の容積でみても20畳分はある) のだが吸音処理ゼロで超ライブ。 それもあってか、やたらパワーを食われるという心配が無い。 で、ラウドネスコントロールのせいか、 はてまたライブな空間のせいか 中低域以下もどんどこ出てくる。 もちろん、キャビの限界はあるので、 出てくる音は正にドンドコ、という感じなのだが それは仕方ないというものだ。

これまた段ボール素材の円筒(直系70㎜)も用意してあったのだが 現状での音を把握することを優先とした。 聴き進める内にやっぱりハイエンドの寂しさが気になり始めたが これまたトーンコントロールのトレブルをちょいとひねって解決とした。 スピーカーそのものの話からは逸脱するが この時代のプリメインは実に機能が豊富で感心する。 このアンプを見ても、PONOが二系統あってインピーダンスや 負荷容量の切り替えまでついている。 TUNER、AUXがある上にTAPEなんか3系統もある。 (TAPE3端子はフロントにあって、これはビクターのお家芸) ラウドネス、トーンコントロールはもちろん、 ハイフィルター、サブソニックフィルターもついている。 モードの切り替えもあって、NORMAL、REVERS、MONO(L+R) Lのみ、Rのみまで選択出来る。 スピーカーも二系統繋げて、OFFポジションもあり。 もちろん機能競争の時代だったと言うこともあろうが それだけユーザーが積極的に音を機械を弄ろうという 気概みたいな物を持っていた証とも言えまいか? なんとも懐かしく、そして今の時代においてもありがたさを感じる。 ラウドネスやトーンコントロールを活用するなどというと 笑われかねない風潮もあるが (諸々フラットで使えるのが一番、と言ったような考え方) 気軽に音の調整が出来るのならそれを積極的に使うのも 悪い話ではないと思う。 今回のケースでいうと、下手をするとツイーター追加 (最終的には必要かもしれないが)や バスレフにしてダクトのチューンなんて話にもなりかねない。 それは大がかりとも言えないか? アンプのコントロールで解決が付くのなら、 それは大歓迎というものだ。
一通り掛けて充分納得を得た。 特にボーカルの聞き取りやすさは優秀で、 英語音痴のよっしーでも発音が明瞭に聞き取れるという シーンが多々あって驚いた。 とどめに、と計算していたわけではないのだが 常用のコンコルドとの切り替え試聴をやってみた。 すると…。
JA-S71には二系統のスピーカーシステムを繋ぐ事が出来、 かつそれをフロントのスイッチで切り替え(A+Bの合わせ技もOK) 出来るのだから話は簡単。 取り敢えずP-610段ボールはB端子に繋いで聴いていたので セレクターをグイッとA端子に回す。 一発でコンコルド側に切り替わるのだが…。
(当たり前!) この場所であまりにも聴き慣れた筈のコンコルドの音だったのだが 正直言っあからさまな音傾向の違い(P-610段ボールとの)にビックリした。 両者の音傾向はまるで違った。 音を聴いて貰えれば一発でわかる違いをわざわざ文章にしようとするから 難しくなるが、何とか頑張ってみよう。 一言で言えばコンコルド105がムード派であるとしたら P-610段ボールは写実派であるということ。 P-610から切り替えた直後のコンコルド105の音は 幻想的というか夢幻的であるとすら感じられたものだった。
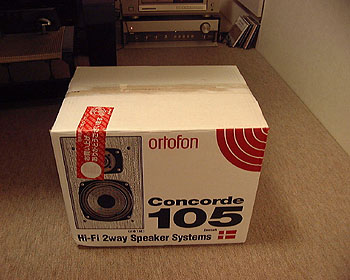
まずそのサイズからは到底信じがたい奔放で開放的な 低域が印象に残るはずだ。 何しろ分厚い。 約30畳の空間(実効20畳だとしても)を相手に どうどうと渡り合えるのだからいかに凄いかわかって貰いたい。 (使っている人にとっては何をか言わんや、だが) そこに実に嫌みのない中高音が載っかっている。 とにかく嫌みがない。角を立てないというか棘がないというか、 である。 これはとにかくこれで充分。 というか140×218×207mmのミニスピーカーが 大空間を相手に鳴り渡るのだから文句なんか言えた義理ではない。

一旦同じ場所、同じ条件でP-610段ボールの音を聴いてしまうと コンコルドの足りないところが俄然耳についてしまう。 鮮烈で、それでいて暖かみのある弦の切れ込みとか 芯があって、それでいて厚みも忘れないピアノのアタックとかいう話になると 段ボールキャビネットではあってもP-610の圧勝となってしまう。 一言でいうと、P-610の方が遥に本格派なのだ。

みたいに思われてしまうかもしれない。 だが、そもそもこれだけ広い空間を相手にさせる事が 間違っていると言えば間違っている。 いかに名器であっても10㎝2Wayが相手に出来るエアーボリュームには 限度がある? そして音作りの傾向が違うといえば違う。 …と、コンコルドを擁護するような事を書きつつも 同時にP-610の潜在能力の高さに舌を巻いていたりもする。 確かに16㎝とコンコルドよりは大口径だが あくまでもフルレンジ一発であり、今回のキャビは 段ボールなのだから、そう考えるとこちらもただ者ではない。

業務用(BGM用)としては最適なのでこれからも生き残るだろう。 だが、正直いうと僕はもう頭の中でP-610を使った自作スピーカーの 図面を書き始めてしまっている。 この後一気に自作に突入!…と行きたいが それはなかなか難しい。 何より置き場所が問題だ。 (教室で使用) お金も問題だし、製作する時間の確保も問題だ。 さあ、どうしよう? どうしたら良いのだろう。
一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。
|